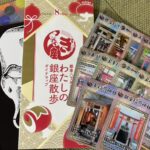英信寺(読み方はえいしんじ)は、東京都台東区にある浄土宗の寺院。
ご本尊の阿弥陀如来の他、商売繁盛の神様で知られる大黒天を祀っていますが、こちらの大黒天は弁財天と毘沙門天とも融合した三面大黒天。
しかも弘法大師空海の作。
福徳開運・商売繁盛の守り神で、ガラス越しに拝観することができます。

目次
・ご本尊・ご利益
・歴史
・山門・境内
・本堂
・三面大黒天
・御朱印・お守り・おみくじ
・入谷七福神とは?
・アクセス
・近くにある神社・寺
英信寺のご本尊・ご利益
山号は紫雲山。
院号は常倫院。
宗派は浄土宗。
山号の「紫雲」とは、臨終にあたって阿彌陀仏が来迎される時に乗ってくる紫色の雲のこと。
また、紫はめでたく高貴な色とされています。
ご本尊は阿弥陀如来。
下谷七福神の三面大黒天も祀っています。
英信寺の歴史
1631年(寛永8年)に、関東十八檀林の1つである霊巌寺(れいがんじ)を創建した雄誉霊巌(おうよれいがん)が開山。
当初は「紫雲庵」と呼ばれる小さなお堂でした。
1656年(明暦2年)、亀山藩の松平康信の三男・松平英信の菩提を弔うために寺院として整備され、英信の姉が英信の木像を作って安置したことから名称が「英信寺」に改称されました。
松平三家の菩提寺として亀山藩の松平家の他、大分県の杵築藩松平家、静岡県の小島藩松平家の藩主のお墓もあります。
英信寺の山門・境内
大通りから通じる道の先には、「紫雲山」と書かれた瓦葺きの山門。


こじんまりとした境内は、左側に寺務所、奥に本堂と大黒天堂。

そして、右側には杵築の松平家が奉献した「東叡山有徳院殿」と書かれた大灯篭。
東叡山有徳院殿は8代将軍徳川吉宗の戒名で、その墓所は東叡山寛永寺にあります。
大灯篭は境内中ほどにもう一つあり、こちらは開基の松平家が奉献されています。


英信寺の本堂
1973年(昭和48年)に大改修された本堂。
本堂の屋根には、逆さ獅子とぼたんの花の飾り。
奥(屋根のてっぺん)には鳩の飾り瓦も。
堂内にはご本尊・弥陀三尊像が安置されており、中央に阿弥陀如来(立像、上品下生印)、右に観音菩薩、左に勢至菩薩を従えています。

本堂正面には巨大な数珠。
滑車で吊り下げられており、南無阿弥陀仏と念仏を唱えながら数珠つなぎになった玉を引っ張るとよいそうです。
この巨大な数珠は、薬王山医王院福泉寺(横浜)でもみられます。

英信寺の三面大黒天
本堂向かって左側には、弘法大師空海の作といわれる三面大黒天が安置されています。
創建当初からある入谷七福神の一つです。
正式名は三面六臂大黒天。
真言は「オンマカキャラヤーソワカ」。


三面大黒天は、正面に大黒天、向かって右は弁財天、左が毘沙門天、後部は宝珠形光背のご尊像。
全体が黒く、正面を向いている大黒様のお鬚も3つに分かれてるなど、一般的な大黒天とは大きく異なる風貌をしています。
毘沙門天は四天王のひとりで北方の守護神。
邪気を踏みつける姿で知られる最強の武神で、特に勝負運のご利益が。
弁財天は芸術・福徳・蓄財のご利益がある神様として知られています。
仏教の守り神である三つの顔を持ち、出世・開運・商売繁盛のご利益パワーが強そうです。
ちなみに、三面大黒天は金剛院(豊島区)にもあります。
英信寺の御朱印・お守り・おみくじ
英信寺の御朱印やお守りなどの授与品は1月のみとなっているようです。
御朱印では、ご本尊の阿弥陀如来と下谷七福神「三面大黒天」があります。


入谷七福神とは?
入谷七福神は英信寺の三面大黒天の他、真源寺(福禄寿)・寿永寺(布袋尊)・飛不動尊正宝院(恵比寿神)・弁天院(朝日弁財天)・法昌寺(毘沙門天)・元三島神社(寿老神)の7社寺。
七福神巡りが始まった頃は社寺それぞれで御開帳日を定めていましたが、1977年(昭和52年)からは7社寺そろって御開帳日(毎年1月1日~7日)を定め、七福神めぐりがおこなわれています。
集印用の専用色紙は3種類あり、各社寺を巡拝して集める七福神の分身もあります。

英信寺の詳細
英信寺へのアクセス
- 東京メトロ日比谷線:入谷駅4番出口より徒歩3分
英信寺近くのおすすめ神社・寺
| 小野照崎神社 | 「男はつらいよ」の寅さんも!断ち物祈願による願掛けで有名。 |
|---|---|
| 法昌寺 | たこ地蔵や入谷七福神毘沙門天(下谷七福神巡り)で有名な寺院。 |
| 真源寺 | 入谷鬼子母神と朝顔まつりで有名。また、入谷七福神福禄寿が祀られています。 |
| 太郎稲荷神社 | 一葉さんの「たけくらべ」に出ている、住宅地の中の稲荷神社。 |
| 三島神社 | 雷井戸の伝承のよる「不落祈願」や「不落守」で有名。境内には火除稲荷社が鎮座。 |
| 元三島神社 | 「三島さま」として知られ正岡子規ゆかりの地。定期的に変わる手花水と御朱印も。 |